
【お膳のメニュー☆】
(左上)
千六本のゴマ酢がけ
(右上)
はりはり漬け
(中央)
するめの唐揚げ
(左下)
桜飯
(右下)
伊勢豆腐
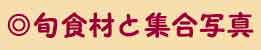
●1月(睦月)のお膳という事で、お正月料理を格別に意識してみました。
行事食については、清水先生が「小豆がゆ」を推して来てくれました。 👀
破魔開運の小豆は、お江戸ながらのメニューですよね。
うれしく取り入れ、「お江戸の冬」を意識するならと、この月は乾物も少しメニューに加えました。

私の所持する料理資料と、清水先生が持って来られた資料の中から、色々に検討をしたのですが。
伊勢豆腐は、これらの資料の中で私が一目惚れして、加えました。 (〃∇〃)
色合いと材料が、いかにも江戸だと♡
渋い仕上がりに、独りでときめいておりました。

また「するめの唐揚げ」は、今は亡き母のメニューです。
昭和20年頃の出版社の忘年会での、定例メニューだったんだそうですよ。 👀
当時は、するめも安かったんでしょうね。
昨今では、乾物の方が「手が加わっている分、割高」なのだと、清水先生から習いました。 😅💦

桜飯も、私の所蔵する資料の中から選んでみました。
私が料理の仕事をするようになって、半年くらいだったでしょうか。
こちらの資料を手に入れて、お江戸の糧飯の種類の豊富さに、ワクワクとしたものでした。
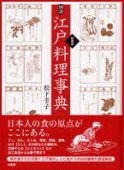
また「炙りミカン」は、清水先生が見つけて来て下さったレシピなのですが、念のためにネットで調べてみると、なんとHPが存在していましたっ。
「みかんを焼くなんて、どうなんだろう」なんて話していたのに、驚きでした。 😅💦
その記事を清水先生にも見て戴いて、栄養面などでチェックして戴いて、記事にしています。

様々ありましたが、今月のお膳の写真の仕上がりも「いかにも、お江戸っぽい♡」と。
・・・またもや、ひとりホクホクして喜ぶ私なのでありました。 (^▽^;)
(2018年1月31日 文責・山野亜紀)
(料理・器/清水紀子)
<お正月から、日本で行われてきた行事と、行事食
1.お正月(1日)に行われる行事
初日の出、初詣、初夢、若水(わかみずは、元旦に家長が汲む、その日1番のお水)
お年玉(家長が、年神さまにお供えしたお餅を家人に配る・・・「年神さまの魂が宿る餅玉(年魂)の意」なので、お金ではなかった。

(行事食)
〇お雑煮・・・(年魂さまが宿った餅)を食べる、の意味。
〇お屠蘇・・・薬草を合わせた「屠蘇散」を浸した酒(一度沸騰させて、アルコール分を飛ばす★)を飲んで、「悪鬼を屠り(ほふり・・・つまり打ち負かし★)、死者を蘇らせる」意味となり、邪気払いと不老長寿を願う。
(おまけ)
〇祝い箸・・・両端が細い箸を使うのは、片方は年神さまが、片方は人が使うとされているからだそう。

2.人日の節句(7日)の行事
人日(じんじつ)とは、古代中国では「1日が鶏の日、2日が狗(犬)の日」・・・という風習があり、「人の日」というのも存在した。
・・・それが日本に伝わり、暦に取り入れられたのが、五節句である。
五節句とは・・・「人日(1月7日)、上巳(じょうし)(3月3日)、端午(たんご)(5月5日)、七夕(しちせき)(7月7日)、重陽(ちょうよう)(9月9日)」の5種。
(行事食)
七種粥(ななくさがゆ)・・・もとは、7色の野菜ではなく、7種の具材を入れるモノであったそうだ。
3.鏡開き(8日)
年神さまにお供えした鏡餅を、一家円満と反映を願って、木槌で叩き割って食べる。 (お正月の終りを意味する)

(行事食)
お汁粉や、揚げ餅など。
どちらも、固くなったお餅を美味しく食べるためですが、「歯固め」の意味もあります。
・・・固いモノを食べて、歯を丈夫にし、健康で長生きできるよう願います。
4.小正月(15日)
●左義長(さぎちょう)
豊作を祈る「もち花」を飾り、年神さまを送る左義長の儀式(別名・どんど焼き)で五穀豊穣と、無病息災を願う。

●もち花
柳の枝に、紅白のもちを付けて稲や桜の花に見立てたモノで、養蚕が盛んな土地でなら、「まゆ玉」と呼ばれる事も。

(行事食)は、小豆がゆです。

〇2018年1月の旬食材(鯛、春菊)
【レシピ】
小豆がゆ(1月) 桜飯 伊勢豆腐 するめの唐揚げ はりはり漬け 千六本のゴマ酢がけ ポン酢しょうゆ 炙りミカン
【エッセイ】
☆「好かれている証拠だね?春菊と鯛、今こそこの時期、日本人」~睦月の旬エッセイ(2018年) 第57話 正月明けて、武劇を2本立で!(2018年1月)






