春の日に、漁師町でも、ひなまつり☆
とれとれの魚で、何を選ぼう、
今日のごちそう、海鮮ちらし♡


- ★2人分の材料です。
- 米‥‥‥2合
- 昆布(5cm)‥‥‥1枚
- (a)酢‥‥‥50ml
- (a)砂糖‥‥‥大さじ1.5
- (a)塩‥‥‥小さじ0.5強
- 青シソ‥‥‥5枚
- 白いりゴマ‥‥‥小さじ1
- マグロ‥‥‥60g
- 鯛‥‥‥60g
- サヨリ‥‥‥一尾分
- 卵‥‥‥2個
- [b]砂糖‥‥‥小さじ1
- [b]塩‥‥‥ひとつまみ
- レンコン‥‥‥5cm
- 《c》酢‥‥‥大さじ2
- 《c》砂糖‥‥‥小さじ2
- 《c》塩‥‥‥ひとつまみ
- 《c》水‥‥‥大さじ2
- 昆布‥‥‥適量
- 木の芽‥‥‥適量
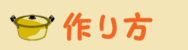

- マグロは食べやすく切って、しょう油を適量を回しかけて漬けに。
鯛とサヨリは、昆布で挟んで昆布絞めにする。 - レンコンは、薄切りにしてさっと茹でて、《c》に漬け込み「酢蓮」にする。
- 米は研いで、400mの水に昆布を加えて、30分以上浸水してから普通に炊く。
- 炊き上がったらすぐに飯台などに移し、(a)を回し入れたら、しゃもじで返しながら馴染ませる。
- 酢飯が人肌に冷めたら、千切りにした青シソとゴマを加えて混ぜ、濡れ布巾をかけておく。
- 卵は溶いて[b]を加え混ぜたら、錦糸卵にする。
- の酢飯に、マグロや食べやすく切った鯛、サヨリ、錦糸卵、酢蓮、木の芽をバランスよく散らす。

●3月3日は、雛祭という呼び方か「桃の節句」というのが一般的なんですが。
実は「上巳(じょうし)の節句」というのが、正式名称なようなんです。 👀
この三つの呼び方は、根っこを辿ると中国でやら日本ででも、それぞれに全然、全く別の意味を持っていたハズなのに、今では合体っ!
日本では、1つの祭りとして行われているというのだそうでして・・・★
ホント、日本って、何でもかんでもごた混ぜにしてしまう処が、良いような、悪いような感じもしますよね。 (^▽^;)
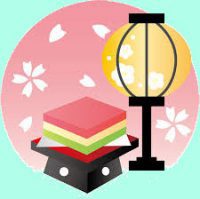
●さて「上巳」が何かと申せば、これって「上旬にある巳(ヘビ)の日」という意味になります。 👀
ヘビが冬眠から覚めて、大地で脱皮を始めるという・・・春先の季節なんですが★
・・・この頃は実は春雨も多くて、体調を崩しやすい時節でもあります。
ちなみに「この時期に中国では、水辺で禊ぎをする風習があった」そうで、その行いがまた「人も、ヘビの如くに古い殻を脱ぎ捨て(脱皮し)て、新しいエネルギーを取り込む☆」というモノであったよう☆ (゜-゜)

またこの時期には「邪気を祓う行事」として、宮中で行われていたというのが「曲水の宴(うたげ)」・・・。
これは現代日本でも、神社などで、年中行事として行われていますよね♡
「うねうねっとした川の流れは、さながらにヘビの様子にも似て」いて、この水の流れに器を浮かべて、盃を乗せては、上流から流します。
そして、自分の前を器が通り過ぎるまでに詩歌を詠む・・・という、えらく風流な行事なのでありました。 😅💦

同じ「流す」という行為でも、これが庶民の場合でなら人形やら、紙を切り取って作った人型で、自分の身体を撫でては、息を吹きかけ。
自らの穢れを人形に移して川に流しますが、これは今でも「流し雛」として、続けられている地域もありますよね。 (゜_゜ )
この紙人形がもとで、当時は貴族の幼女の遊び道具だったモノが今では「雛人形になっていった」のだそうで、そこには後に桃のパワーも含まれて行きました♡
●ちなみに中国では、「桃は、不老不死の仙人の果実」とされていますし。
桃の種には実は、身体を温める効果があると言われているらしいんです。 👀
日本では「古事記」を見ても、桃に関する記述もありますから、今ではすっかり「魔を祓うパワーのある桃」は、上巳の節句には欠かせないアイテムとなりました♡

●はてさて、雛祭りといえば・・・ちらし寿司。
とはいえ、あんまり在り来たりなモノでは面白くないと私と清水先生で2人、頭を悩ませまして・・・。
それならと、「お江戸の春を思わせる魚を、酢飯にのせてみましょう」という流れになりました♡ (^-^)
何しろ・・・お江戸の当時は、マグロは漬けで楽しまれていましたし、さっぱりとした鯛やら、サヨリなどの白身の魚たちは、江戸人の大好物で、とても愛されておりました。

お江戸の当時は、「何処に行くにも歩いて行くしかない、ガテンな時代・人達」であったのに、魚の好みだけは何故だか、さっぱりとしたモノを、ひたすらに愛していたようなんですね。 👀
お江戸の春から呼び起こした、こんな・・・海鮮ちらしで、雛の節句を楽しんでみてはいかがですか?
錦糸卵をふわりと散らせば、豪華で華やかな彩りになります☆

春のおもむき一杯のちらし寿司で、ぜひ食卓を囲んで下さい。
心躍る、春の食膳です。 (^_^)/
(2018.3.5 文責・山野亜紀)
(料理・器/清水紀子)
「つるし雛」って、ご存知ですか?
●7段飾りの雛人形も良いのですが、スペース的に難しくて・・・★ (^_^;)
はたまた、1間のアパートながら、雛のシーズンをちょっとだけでも醸したい!
・・・そんな方には、お江戸の頃に始められたという、リーズナブルな「つるしびな」をいうのがありますよ♡
五人囃子も、三人官女がいなくても、ぽっちりと雛の節句が楽しめます♡ (^_^)v

1.唐辛子
虫が付きにくいため、悪い虫(男)がつかないようにという意味で下げるそうですが・・・うーん、深いですね。 😅💦
2.巾着
おサイフの代わりに巾着を飾る事で、お金に不自由しないように!
うーん、正しいですね(笑)
3.這い子人形
「はいはいする子は、よく育つ」ので、健やかな成長を願って。
・・・たしかに、赤子はハイハイで運動能力を高めると聞きました。 👀

4.桃
邪気を祓う桃は、長寿を願う現れでもあります。
5.三角
ついこの間まで、散薬はビニールやセロファンではなくて、紙に包んで処方されていました。
その場合は、薬を入れて「三角形の形に包む」ので、薬に縁のないよう、無病息災を願って飾るモノのようです。 👀

6.犬
お産が軽く、子だくさんな犬は安産祈願。
子宝祈願の願いに繋がります♡

〇2018年3月のお膳






